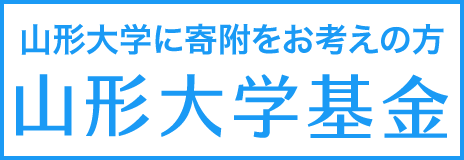2024年9月8日(日)から9月10日(火)にかけて、山形大学小白川キャンパスにおいて、日本地質学会第131年学術大会(山形大会)が開催されました。日本地質学会は、日本における地質学の発展と普及を目指して、1893年に創立された歴史ある学会です。会員は、大学の研究者や学校の教員、企業の研究者、大学生・大学院生、地質学愛好者、高校生などで構成されています。学術大会は、毎年異なる都道府県で開催されており、今年は1986年以来38年ぶりに山形での開催となりました。今回の大会運営は、山形大学理学部および地域教育文化学部の教員や学生が一丸となって取り組みました(図1)。
図1:山形大学学生らによる会場運営の様子。(a): 受付会場では一窓口に2名体制で対応;(b): 学会発表会場で学生はプログラム進行・時間計測の重要な役割を果たしました。
本大会では、最先端研究が口頭・ポスターを通じて発表されました。山形大学からも複数の研究発表が行われ、本学部からは2件の発表(*注1)があり、活発な議論が展開されました(図2)。さらに、ポスター発表では高校生による研究発表もあり、山形大学と共同で研究を進めている学校も参加していました。大学では先生から教わる勉学以外に研究活動があります。もし山形大学で熱心に研究し、新たな知見を発見した場合、その成果を学会で発表し、論文にまとめることで、世界に向けて学術的な貢献が期待されます。
図2:研究発表の様子;(a): 口頭発表の様子(研究受賞者による記念講演);(b): ポスター発表会場(高校生セッション)。
同時開催イベントとして、山形の地質や東北地方の地球科学の魅力を学ぶ巡検も複数実施されました(図3)。山形県内の巡検コースの一つでは、本学部名誉教授であり、テレビ番組『ブラタモリ』山形編で地質解説を担当した大友幸子先生による「山寺と山寺層―地質・歴史・文化地質学」が行われ、参加者は山形の火山地質と文化の融合について学びました。一方で、山形以外の地域では、「阿武隈山地東縁を探る」(主催:東北大学の辻森研究室・武藤研究室)という岩石巡検が行われ、本学部からは変成岩を研究する竹林知大先生が参加しました。
図3:巡検での集合写真。(a): 「山寺と山寺層―地質・歴史・文化地質学」のコース(写真中央最前列黄緑色洋服と明色の帽子:大友先生);(b):「阿武隈山地東縁を探る」のコース(写真中央最前列ハット姿:竹林先生)。
全国の地球科学を研究する多くの人々は、本大会を通じて山形や東北地方の地質、文化、歴史など、その魅力を数多く発見したことでしょう。次に山形大学で全国大会が開催されるのは、おそらく40年後、つまり約半世紀後になるかもしれません。この記事を読んでいるあなたも、ぜひ山形で地球を科学してみませんか?
図4:山形駅に設置された地質学会山形大会の大きな看板。38年振りの全国大会は大成功でした。次回の山形開催はおよそ40年後であろう。
≪注1:地域教育文化学部の発表者とタイトル≫
Ø 竹林(本学部教員)ほか4名: 2030年までの自動車エンジン開発におけるSTEM・環境教育を小中学校の教育内容として考察
Ø 大友(本学部名誉教授)&田宮: 萬世大路栗子トンネル西坑口周辺の流紋岩の岩石記載