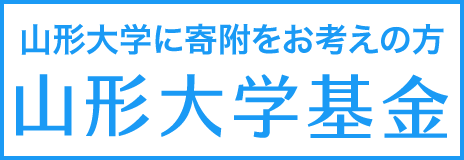2025年3月19日(水)18時から、本学部名誉教授の大友幸子先生が、「大学コンソーシアムやまがた・やまがた夜話(やわ)」にて招待講義を行いました。大友先生は地質学がご専門で、NHKの『ブラタモリ』でも山形県の地質解説を担当されています。講義は山形大学理学部ふすまホールとオンラインで開催され、65人(会場:35人)の市民や地域教育文化学部・理学部の教員と大学生・大学院生が聴講しました。
▲ 大友幸子名誉教授による市民向け講義の様子。会場内は多くの人々が集まりました。
今回のイベントのスローガンは「日本列島はすごい~山形もすごい」で、大友先生は「山形でいつも見ている景色も実はすごい―大地の歴史を語る―」と題し、山形県の地質とそれに関連する文化や歴史についてお話しされました。
大友先生の講義によると、私たちの暮らす山形県には、中生代から新生代にかけて日本海の拡大とともに形成された浅海時代の地層や火山活動の痕跡が残っています。たとえば、海の時代の泥岩や有孔虫化石、火山の時代の凝灰岩や安山岩など、多様な岩石を山形に分布しています。そのとき生成された岩石は、現在の私たちの暮らしにも密接に関わっているそうです。
▲ 講義のタイトル画面。山形県の多くの建物には地域の石材が使われている。スライド写真は大友先生が撮影した山形県郷土館「文翔館」。
講義後は多くの市民や学生が大友先生を囲み、山形県の地質の魅力について熱心に質問する姿が見られました。参加した学生に感想を尋ねると、新しい発見があった意見や大学での研究に役立ちそうな意見が挙がり、学術的に有意義な講義となりました。また、地域教育文化学部の竹林知大先生は「山形県にはプレート運動によるダイナミックな地形変化が各地に残っていて驚いた。いつか学生と一緒に観察に行きたい」と感想を述べられました。
山形県には、海から火山にかけての空間的な広がりと、白亜紀から現代に至る時間的な壮大さが刻まれています。美しい景色を眺めながら、その土地に秘められた地球規模の歴史に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。
▲ 左写真:山寺の地質について紹介する大友先生。右写真:講義終了後の学生からの質問の様子。
本記事の写真撮影:竹林知大先生(山形大学地域教育文化学部 地球科学)
主催:大学コンソーシアムやまがた (https://consortium-yamagata.jp/)
山形大学開催のチラシ :https://consortium-yamagata.jp/?p=7756
開催記事(ゆうキャンパス):https://consortium-yamagata.jp/?p=7857
2025年2月23日に、地域教育文化学部文化創生コースで音楽を専門的に学ぶ学生などが講師を務め、「滝山ブラス」(山形市滝山小学校ブラスバンド部)の指導をしました。
メンバーは「滝山ブラス」出身の教員志望学生を中心に、トランペット2名、ホルン、トロンボーン2名、チューバ、打楽器の計7名。
これまでも、指導者として、学生が地域の小中学校に招かれることは少なからずありましたが、このようにまとまった人数で訪問するのははじめての機会となります。
学生は子どもたちを相手に、姿勢や呼吸法について丁寧にレクチャーしました。
トランペットの指導に耳を傾ける子どもたち
トロンボーンのマウスピースを吹いてみる子どもたち
最後にはミニコンサートを開催しました。
真剣な眼差しで演奏に聴き入っていた子どもたちからあたたかい拍手が送られ、学生たちは音楽の楽しさを伝えられた喜びと充実感を味わいました。
山大生の演奏を熱心に聴く子どもたち
部活動の地域移行に伴う大学の関わりとして今回試験的に実施いたしましたが、双方の負担感の少ないところで展開することができれば継続的に行うことも可能であると考えています。
学生自身が小中高生のときには、同じように学校の先生や地域の指導者から楽器について教えていただくことがありました。そのときのことを思い起こしながら、子どもたちを教え、またその子どもたちが大人になったあかつきには、次世代の子どもたちを教える。そのような循環が、地方における音楽文化の向上につながると考えています。
(地域教育文化学部:佐川馨・名倉明子)
☆山形新聞の取材を受けました。以下よりぜひご覧ください。
URL : https://nordot.app/1270557333296152869?c=113147194022725109
2024年12月22日(日曜)に山形大学小白川キャンパスを会場に、第11回やまがた教員養成シンポジウムをハイフレックスで開催しました。参加者は、64名(対面37名、オンライン27名)でした。山形大学地域教育文化学部・大学院教育実践研究科と公益財団法人やまがた教育振興財団が主催し、山形県教育委員会と東北文教大学の後援をいただきました。
本シンポジウムのテーマは、「これからの山形の教員養成を考えよう」です。現在、山形県では、少子化による長期的な教員需要の減少傾向と、年齢の高い教員層の大量退職による教員需要の高まりという2つの動きがアンバランスに進行しています。そうした中で、教職を志願する学生が減り、教員志願倍率の低下が問題になっています。現在の大きな課題は、「地域や学校現場のニーズに対応した質の高い教師を、継続的・安定的に養成し確保する仕組み」を山形県内にいかにつくるか、にあります。
今年度の第11回やまがた教員養成シンポジウムでは、地域において質の高い教師を継続的・安定的に養成し確保する取組みについて、その現在地と今後の課題について、幅広く関係する皆さんと議論する場とすることを考えました。シンポジウムの報告者は、次の3名でした。
| ① | 「小学校教員体験セミナー」の現在地 |
山形県教育局高校教育課指導主事 叶内有希絵 |
| ② | 地域希望枠による教員養成の特別教育プログラム |
山形大学教授 吉田誠 |
| ③ | 地域や現場ニーズと新しい教員養成のコンセプト |
山形大学教授(副学部長)安藤耕己 |
報告のあとの質疑と意見交換では、東北文教大学の鈴木隆副学長に指定討論をお願いしました。会場からは、「小学校教員体験セミナー」の実施校の広がりを求める意見や、新しい教育学部を山形の教育を変えるきっかけにしたいという意見など、活発な発言がありました。
会場には高校生も多く参加し、新しい教育学部への関心の高さをうかがうことができました。アンケートには、高校生から、次のような声がよせられています。
・実際に小学校教員体験セミナーに参加したのですが、改めて参加した意味を確認することができました。また、自分が、教員を目指すにあたって必要な力を知ることができ、これからの生活で意識していこうと思いました。ありがとうございました。(高校生)
・ただ教員になりたいということだけではなくて、教育面の課題にふれることで、自分の中での教育に対するイメージを大きく変えることができた。見方が変わった。ありがとうございました。(高校生)
このほか、アンケートには、本テーマでの継続したシンポジウム開催を要望する声もありました。ご参加いただいた皆さまに感謝申し上げます。ありがとうございました。
(江間史明)
パネリストの報告