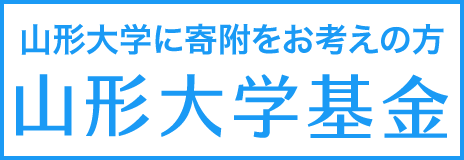山形大学地域教育文化学部は、2024年11月24日(日)、山形県で初となる世界最大の地球科学研究用掘削船「ちきゅう」との衛星中継を活用した特別講座を開催しました。この中継は、宮城県沖に位置する「ちきゅう」と山形大学、さらに「ちきゅう」の母港である静岡を結んで行われました。山形大学会場には子どもから大人まで約140人が集まり、最先端の地球科学研究について理解を深めました。
▲ 上の写真は山形大学小白川キャンパスでの「ちきゅう」との衛星中継を活用した特別講座の様子。写真に移る映像には中継先の「ちきゅう」には山形大学大学院理工学研究科博士課程の萩野穣さん(古生物学)、山形会場の司会進行・解説は竹林知大先生が務めた。竹林先生の赤いスーツは、IODP ECORDから給付された「ちきゅう」の専用スーツ。
「ちきゅう」は現在宮城県沖約200kmで、日本海溝の岩石を採取する国際深海科学掘削計画(IODP)の第405次研究航海「JTRACK」が実施されています。この研究は、2011年3月11日に発生した東日本大震災に関連するプレート境界型地震の解明を目的としており、日本をはじめ、アメリカ、フランス、スペイン、イタリア、ドイツ、オーストラリア、カナダの研究者が参加しています。調査掘削は2012年以来12年ぶりで、今年9月21日には世界最深の7877.5メートル地点で岩石採取に成功しました。
▲ 上の写真は左から「ちきゅう」と「掘削パイプ」「ドリル(ライザー掘削)」「ドリルオペレーションルーム」である。撮影:竹林知大(IODP Exp. 386 2022年)
本講座では、地域教育文化学部教員で2022年に「ちきゅう」に乗船経験のある竹林知大先生(地球科学)が司会と解説を務め、船の基本情報や地球科学研究の魅力についてお話しされました。中継では、日本や海外の研究者が登場し、山形大学大学院理工学研究科博士課程の萩野穣さん(古生物学)が「ちきゅう」の研究機材を紹介しました。
▲ 上の写真は左が実際に生中継で映し出されている「ちきゅう」の櫓。右が萩野さんの解説している姿。
質疑応答の時間では、小学生から大人まで多くの質問が寄せられ、「ちきゅう」の研究者や萩野さん、本学部の竹林先生がそれぞれ分かり易く応答しました。講座の終盤には「いつか『ちきゅう』に乗ってみたいですか?」と会場に問いかけたところ、子どもから大人まで多くの参加者が「乗ってみたい!」と声を上げながら手を挙げる姿が見られました。講座終了時には盛大な拍手が起こり、とりわけ子どもたちが手を高く挙げて送った大きな拍手が印象的でした。
現在、「ちきゅう」では、日本を主導に世界中の研究者たちが集まり、東日本大震災の謎を物質科学的に解明するために日夜研究を進めています。この取り組みは、将来のプレート沈み込み帯における地震予測や防災・減災対策に大きく貢献する可能性を秘めており、人類共通の課題に挑む重要なプロジェクトです。山形からも、ぜひ彼らの挑戦を応援し、『地球・ちきゅう』の科学に注目をしてみてください!
≪謝辞≫当日の山形大学会場では、地域教育文化学部と理学部から有志の学生さんが運営・撤収の支援がありました。この場をお借りしてお礼申し上げます。
参考情報
(1)2024年11月25日山形新聞朝刊に掲載
(2)IODP Exp. 405 JTRACK: 2024年進行中研究『東北地方太平洋沖地震後の時空間変化を捉える』:山形大学大学院理工学研究科博士課程の萩野穣さん(古生物学)「ちきゅう」乗船 (2024)
(3)IODP Exp. 386『東北地方太平洋沖地震の古履歴解析』:竹林知大先生「ちきゅう」乗船 (2022)