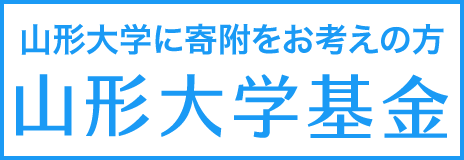地域教育文化学部3年次の授業科目である「フィールドプロジェクトC4(食育・地産地消推進プロジェクト)」において、やまがた食育・地産地消ガイド2022&2023を制作・発刊しました。
これまでに2020と2021を発刊してきましたが、昨年度は費用の面から発刊できませんでした。今年度は、「公益信託荘内銀行ふるさと創造基金」様より助成をいただき発刊することができました。
主な内容は、①山形県の地場産の食材や食品(蕎麦、だだちゃ豆、さくらんぼ、平田赤ねぎ、うまいたれ、青菜漬け)を使ったレシピ紹介、②地産地消に取り組むお店紹介(インタビュー)、③米沢の「かてもの」文化について(特集)、④華のある郷土料理(特集)、⑤食育ワークショップについて(活動紹介)となっています。本活動を通して学⽣⾃らの⾷育や地産地消に関する知⾒も深まりました。⾷育の重要性が⾔われている中で、⼤学⽣を中⼼とした若い世代が郷⼟料理や地域の特産⾷材についての情報を発信することによって、これまで関⼼を⽰していなかった同世代の⼈たちに少しでも興味を持ってもらうきっかけを作ることができれば幸いです。
今後山形県内で配布予定ですが、その他希望者には、送料⾃⼰負担にて無料で配布いたしますのでご活用いただければと考えています。近年、持続可能な開発⽬標(SDGs)の達成に向けた活動が多く⾏われている中で、⾷育活動も、SDGs の達成に貢献できるものだと考えられており、注⽬されています。本学のYU-SDGs EmpowerStationへも本活動を登録しています。今後、様々な関連団体との連携を模索したり、ご寄付をいただきながら本活動を継続し、SDGs の⽬標達成への貢献ができればと考えています。
詳細は、学術研究院 准教授 楠本健⼆(栄養学/地域教育⽂化学部担当)
TEL 023-628-4464またはE-mail. kusumoto@e.yamagata-u.ac.jpまでご連絡ください。
地域教育文化学部では,令和6年度新入生の父母等を対象に学部説明会を開催します。
学部の紹介や就職状況等をご説明しますので,ご出席くださいますようお願い申し上げます。
日時:令和6年4月3日(水)(入学式当日)
10時00分から1時間程度
場所:山形大学小白川キャンパス(山形市小白川町1-4-12)
基盤教育1号館1階112教室
※新入生控室:基盤教育1号館1階113教室
・駐車スペースを確保できないため,自家用車での来場はご遠慮願います。
・4月3日(水)当日は、小白川キャンパスから入学式会場まで臨時バスが運行します。
(臨時バスは12時から運行開始予定です)
・令和6年度山形大学入学式については,山形大学ホームページをご覧ください。
https://www.yamagata-u.ac.jp/jp/information/important/20240215/
毎年恒例の人気イベント「やまぎん県民ホール オープンハウス2024」における企画、ロビーリレーコンサートに、地域教育文化学部文化創生コースで音楽を学ぶ学生たちが登場します!『目覚めよ五感!やまぎん県民ホールを楽しみつくそう!』をテーマとした施設開放イベントになります。山形の技術と伝統がちりばめられた魅力あふれるやまぎん県民ホールのロビーを会場として、学生たちが用意した全25曲により、オープンハウスイベントを盛りあげます!クラシック音楽やミュージカル、今流行りのJ-POPなどの多岐に渡り、地域のみなさまに楽しんでいただけるようなプログラムをご用意いたしました。
地域教育文化学部文化創生コースでは多くの学生が音楽を専門的に学んでいます。学生たちは地域のみなさまとの協同の学びにも積極的に挑戦しており、学内外をあわせて年間120件以上、演奏の機会を得ています。本イベントには2022年より毎年参加しており今回で3回目の出演となります。ぜひお気軽に足をお運びいただき、学生たちへの応援をお願いいたします!
開催日時:2024年3月24日(日)10:00〜15:00
会 場:やまぎん県民ホール1階ロビー
企画運営:地域教育文化学部文化創生コース・音楽研究会
料 金:無料(事前申し込み不要・開催時間中随時入場可)
イベントHP:https://yamagata-bunka.jp/event/2024/03/24040999.html
学術研究や課外活動、社会貢献活動等を通じて、特に顕著な業績を挙げた学生又は学生団体を表彰する「地域教育文化学部等学生表彰式」を2月19日(月)、小白川キャンパス(山形市)で開催しました。
令和5年度は15個人・4団体の受賞が決定。中西正樹学部長より、主に課外活動での顕著な活躍を残した学生たちへ賞状と記念品が手渡されました。中西学部長は、「皆さんの活躍が山形大学の名を高め、他の学生にとっても励みになっていることを嬉しく、また有難く思います。さらなる活躍とより一層の成長を期待しています。」と激励のメッセージを贈りました。
受賞学生の皆さん、おめでとうございます。
なお、今年度受賞学生のうち4年生については、3月25日の卒業記念式典にて表彰予定のため、この日の参加者には含まれておりません。
【令和5年度受賞者】(順不同、複数の功績がある場合は代表的なものを掲載しています)
■ 小野 凜香(地域教育文化学部4年)
… 第44回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール声楽部門 第4位
■ 青山 千紘(地域教育文化学部4年)
… 第14 回ヨーロッパ国際ピアノコンクール ディプロマ賞
■ 阿部 花音(大学院社会文化創造研究科1年)
… 第24回大阪国際音楽コンクール声楽部門オペラコース 入選
■ 佐藤 亜美(大学院社会文化創造研究科2年)
… 第2回東京国際管弦声楽コンクール新進声楽部門 審査員賞
■ 小島 彩乃(地域教育文化学部2年)
… 第6回 Kフルートコンクール大学生・一般の部 優秀賞
■ 村山 依吹(地域教育文化学部3年)
… ブルグミュラーコンクール 2023東北ファイナル高校〜一般部門 銀賞
■ 谷川 円香(大学院社会文化創造研究科1年)
… 未来の作曲家コンサート in 東北 2023
■ 柴崎 茉莉香(地域教育文化学部2年)
… 第45回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール 審査員賞
■ 加藤 澄華(大学院社会文化創造研究科1年)
… 第40回JPTAピアノ・オーディション 全国出場内定
■ 男子バレーボール部(代表:佐藤 優大)
… 第76回秩父宮賜杯全日本バレーボール大学男子選手権大会 東北代表出場
■ 剣道部男子(代表:土田 悦司)
… 第71回東北学生剣道優勝大会 準優勝
■ 剣道部女子(代表:秋山 理菜)
… 第49回東北女子学生剣道優勝大会 優勝
■ 小野 萌子(地域教育文化学部1年)
… 第57回東北女子学生剣道選手権大会 優勝
■ 佐藤 悠月(地域教育文化学部1年)
… 第57回東北女子学生剣道選手権大会 準優勝
■ 岡田 悠(地域教育文化学部4年)
… 第76回東北学生陸上競技対校選手権大会 女子100m・200m第1位
■ 阪 希望(地域教育文化学部4年)
… 第76回東北学生陸上競技対校選手権大会 女子100mH第1位 400mH第2位
■ 齋藤 兼信(地域教育文化学部2年)
… 第76回東北学生陸上競技対校選手権大会 男子400mH第1位 男子十種競技第2位
■ 遠藤 奈那(地域教育文化学部1年)
… 第76回東北学生陸上競技対校選手権大会 女子三段跳第1位,女子走幅跳第2位
■ 陸上競技部女子4×100mリレーチーム(代表:原 伶奈)
… 第76回東北学生陸上競技対校選手権大会 女子4×100mリレー第1位