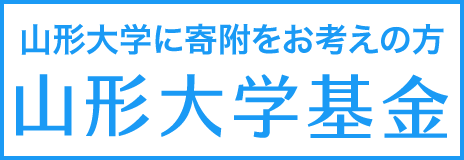その後は、学生企画で①段ボールベッド組み立て新旧比較、②段ボールベッドで寝る体験、③非常持出品(100円均一商品等を含む)の事例紹介、④備蓄食展示と試食、⑤体育館避難者一人当たりのスペースや通路の配置紹介などを行いました。各コーナーは担当学生が説明をさせていただき、住民の皆さまからも積極的な質問が多数出されて交流をすることができ、好評を得ました。最後は自治会の皆さまと一緒に芋煮汁をご馳走になりました。
後期は、地域の皆さんや留学生の方たちにもご案内して、炊き出し訓練などの研修イベントを企画していきます。是非ご参加ください。
卒業、修了を迎えられた皆さんへ
このたび、卒業、修了を迎え学位を授与された皆さん、卒業ならびに修了、誠におめでとうございます。すべての卒業生・修了生の皆さんに、心よりお祝いを申し上げます。
皆さんは、新型コロナウイルスが猛威を奮った真っ只中、この山形大学で勉学に励みました。小中高と対面による授業が当たり前に過ごしてきた皆さんにとって、大学に入った途端にオンライン授業を強いられ、それを受け入れ、その中から知識を得ることは非常に大変だったことと思います。また、仲間と親睦を深めるうえで重要なサークル活動は自粛を余儀なくされ、自らが手を動かし、様々な知識や技術を身に着ける実験・実習ですらもオンラインになったことは、大学生活自体に大きな不安を覚えたことと思います。このように当たり前でないことを当たり前にすることは、並大抵の努力ではなかったはずです。皆さんが本日手にしている学位記には、皆さんが並大抵でなかった努力を一人一人がしたという証でもあります。そして、大学が授与する学位記は、皆さんがそれぞれの専門分野において一定の知識や能力、研究業績を修められたことを証明するものであります。そのことにぜひ自信をもって、次の一歩を歩んでいただきたいと思います。
さて、皆さんはこれから一人一人の人生を歩むことと思います。社会人になる方もいれば、大学院に進学して自らの専門を極める方もいると思います。皆さんそれぞれがこれからの人生を歩むなかで、目の前に大きな壁が立ちはだかり、挫折しそうになり、時には逃げだしたくなることがあるかもしれません。その時は、コロナという大きな壁を自らの力で乗り越え、学位を取得したということを思い出してみてください。皆さんは、コロナ禍の中で学業を修める上で、いろいろな方面から自ら考え、解決したことと思います。こうして皆さんが大学生活の中で1つ1つ積み上げてきたものは、大きな困難をも乗り越える力になると私は信じています。それでも解決できないこともあるかもしれません。その時は一人で抱え込まず、是非この山形大学を訪ねてください。私をはじめ、皆さんの研究室の先生は皆さんと一緒に親身になって考え、きっと解決の糸口を見出してくれると思います。いつまでも本学は皆さんの味方です。
最後に、私から卒業・修了する皆さんへ1つお願いがあります。それは、本日皆さんが学位記を手にできたのは、皆さんの努力だけではなく、たくさんの方の支えがあったからという感謝の気持をいつまでも持ち続けてほしいということです。卒業を目指して切磋琢磨しながら一緒に頑張ってきた友人や皆さんを陰ながら支えてくださったご家族をはじめ、この世の中はたくさんの方との繋がりによって成り立っています。その繋がりの中で生まれる感謝の気持ちを常に持ち続けていただきたいと思います。
また、コロナ禍は我々の生活を取り巻く経済をも大きく変化させましたが、安心して学生生活を送ることができたのも同窓会や地域の方々からの支えがあったからです。新型コロナウイルス感染症により、我が国の経済が厳しいと言われながらも、同窓会からの支援や多くの方から寄付が寄せられました。このように多くの皆様から支援いただく度、いかに学生の皆さんに大きな「期待」が寄せられているかということを、私自身実感しました。
この予測不可能な時代、世の中にはたくさんの課題が山積していますが、本日、卒業・修了を迎える皆さんが、本学で学んだたくさんの知識を活かして、解決してくれることを心から願っております。皆さんの人生の新たなステージへの出発を心からお祝い申し上げ、私からのメッセージといたします。本日は誠におめでとうございます。
令和5年9月22日
山形大学長 玉手英利
9月3日(日)、山形市少年自然の家にて「秋祭り」が開催されました。私たちは、本学部で開講されている「芸術アウトリーチ基礎」での訪問演奏の第2弾として、野外ステージでコンサートを行いました。
アンサンブルでは、ソプラノ二重唱やフルートとヴァイオリンの二重奏による「ジブリメドレー」、クラリネット二重奏による「ホールニューワールド」、金管楽器による「残酷な天使のテーゼ」などを演奏しました。声や楽器ごとに、それぞれ異なる音色の魅力を楽しんでいただけたのではないかと思います。
ソロでは、フルートによる「愛の挨拶」「春よ、来い」や、声楽による「花は咲く」などを披露しました。表情豊かでうっとりするような惹きこまれるメロディーが会場全体に響いたのではないでしょうか。
またプログラム後半には、「Syugo’s music」としてYouTubeや各地での音楽活動も精力的に行う石谷脩悟のピアノソロをお届けしました。即興での「アンパンマンメドレー」に加え、「可愛くてごめん」や「絆ノ奇跡」などの最新の流行ソングを演奏し、お客さまも最高潮に盛り上がってくださいました。
演奏を聴きに足を運んでくださった皆様、ステージの設営や音響などに携わってくださった方々、本当にありがとうございました。
(文化創生コース 2年岩澤心音)
8月8日に、「令和5年度やまがた学校改革推進協議会」の第1回を対面とオンラインのハイフレックスで開催しました。この協議会は、文部科学省「教員研修の高度化に資するモデル開発事業」の一環として実施したものです。当日の参加者は、本事業に関わる山形県内の学校および山形県教育委員会、山形県教育センターの関係者など、42名(対面参加30名、オンライン参加12名)でした。山形新聞と本学のプレス・リリースで本事業について知った宮城県の現職教職大学院生の参加もありました。
現在、日本の教職員は、忙しく勤務しているにもかかわらず、十分な研修時間が確保されていません。「学びたいけど学べない。」という状況が、多忙感をいっそう強めています。このため、現場で学ぶ教師をエンパワーする学校内外の教員研修の充実が、喫緊の課題になっています。こうした課題の克服を目指し、教育実践研究科と地域教育文化学部では、山形県教育センター、山形県教育委員会と共に、全国に先駆けた新たな教員研修のモデル開発に着手しました。今回の協議会は、そのスタートとして企画されたものです。
当日は、出口毅副学長の挨拶のあと、前半は、中西正樹研究科長が座長をつとめ、次の報告がありました。
(1)本事業の全体像とねらい
(2)山形県教育センターの「学校マネジメント講座」の進捗状況
(3)本事業で整備する学校内研修スペース「学びカフェ」について
報告の中心は、本プロジェクトにおいて共有すべき哲学(「Open, Transparent, Flexible, Accountable」)の提示と、その具体例としての公立はこだて未来大学、河北町立谷地南部小学校の取組みの紹介でした。(「哲学」とは、「基底になる考え方」を意味します)。忙しさの中で、教職員一人ひとりの個性的な「人となり」や実践は共有されず、見えなくなりがちです。本プロジェクトの「学びカフェ」は、それを打開することを目指し、各校の状況に即した柔軟な運営を目指します。
協議では、「世界と比較して、日本の教員の自己研修にかける時間の減少が印象的」という指摘や、「日本の教員は、パブリックな面とプライベートな面が重なる多面的な存在である」という指摘がありました。
前半の報告の様子 後半の対談による問題提起
後半は、「新人教師の悩みとこれからの研修に期待すること」として、ディスカッションを行いました。佐藤瑞紀さん(新庄市立新庄小学校教諭、教職6年目)と森田智幸准教授による対談の問題提起のあと、江間史明教授のコーディネートにより参加者同士で話し合いをしました。話し合いでは、「どこの学校でも多忙感があり、若手の先生方が悩んでいる現実があるのだと実感した」という指摘がありました。
グループで協議する参加者① グループで協議する参加者②
協議会後の感想では、参加者から、次の声がありました。「学びカフェの構想が今後、山形県で広がり、どこの地域でも、学校が大学や県教育センターと連携しながら児童・生徒の学びをサポートできるよう、レベルアップできるようになることを期待したいです。」「皆様の熱い思いが伝わってくるとともに、新しいプロジェクトへの期待感がこみ上げてきました。」
今年度の本協議会は、第2回を12月17日(日)、第3回を来年の2月15日(木)に予定しています。ご関心をお持ちの皆さんの参加をお待ちしています。
7月29日(土),小白川キャンパスにおいてオープンキャンパスが開催されました。
地域教育文化学部では,述べ352人の皆様に来場いただきました。午前・午後の二部制とし,「全体説明会(学部説明・入試説明・学生生活紹介)」の後,各コース・分野に分かれて「キャンパスツアー&学生・教員との交流会」を行いました。当日は猛暑ということもあり,キャンパスツアーは希望者のみとなりましたが,現役大学生との交流や教員への質問を通して,大学への理解がより深まったことと思います。暑い中足を運んでいただき,ありがとうございました。
当日おいでになれなかった方向けに、本学部のホームページに関連する情報(学部紹介、各コース紹介等)を掲載しておりますのでご覧ください。
全体説明会の様子
交流会の様子
キャンパスツアーの様子